こんにちは、Part1では赤ちゃんの睡眠の基本と新生児期の寝かしつけテクニックをご紹介しました。
Part2では寝かしつけのテクニックと、多くのママを悩ませる夜泣き対策について解説します!
新生児期(0〜3ヶ月)の寝かしつけテクニック
この時期の赤ちゃんにとって最も重要なのは「安心感」です。
お腹の中にいた時の環境に近づけることで、赤ちゃんはリラックスして眠りにつきやすくなります。
1. おくるみで包み込む
赤ちゃんには「モロー反射」と呼ばれる、驚いた時に手足を広げる反射があり、これが睡眠中に起こると目が覚める原因になります。
おくるみで優しく包むことで、この反射による目覚めを防ぎます。
2. ホワイトノイズを活用する
子宮内で赤ちゃんが聞いていた音に似たホワイトノイズは、驚くほど効果的です。
ドライヤーの音、掃除機の音、レジ袋のカシャカシャという音など、意外なものが赤ちゃんを落ち着かせることも。
ホワイトノイズはYouTubeにもあるので一度試してみるといいと思います。
3. 抱っこの工夫
縦抱きよりも横抱きや対面抱きで、全身を支えるように抱くと安心感が増します。
軽く揺らしながら「シー」という小さな音を出すと、胎盤の音に似た環境を作れます。
生後4〜6ヶ月|睡眠リズムが芽生える黄金期
この時期は赤ちゃんの体内時計が徐々に形成され、寝かしつけ習慣を確立するのに最適な時期です。
上手に習慣づけをすると、将来的な睡眠パターンの土台になります。
1. 寝かしつけルーティンを作る
毎晩同じ順序で行動することで「これから眠る時間だよ」という信号を脳に送ることができます。
例えば
- お風呂(リラックス効果)
- パジャマに着替え
- 部屋を少し暗くする
- 絵本の読み聞かせ
- 授乳
- 寝かしつけ
この流れを毎晩同じ時間に行うと、赤ちゃんは自然と眠りに向かう準備を始めます。ルーティンは20〜30分程度の短いもので十分です。
2. 日中の活動量を適切に
この時期は寝返りなどの新しい動きに挑戦する時期。
日中はたっぷり体を動かす遊びを取り入れましょう。ただし、夕方以降は穏やかな活動に切り替えるのがコツです。

長女は夕方に公園で遊ばせると興奮して夜全然寝なくなることに気づきました。その後は朝〜昼に公園に行くようにしたら、夜の寝かしつけが少しスムーズになりましたよ。
少し遠出したりいつもと違う環境を体験すると、全然寝れないことも…その時はもう、「しかたがない」と諦めました。そう思うことで気持ちも少し楽になりました。
3. パジャマと日中着を区別する
赤ちゃんの首が座り、着替えがしやすくなったら、パジャマを寝るときの合図として活用しましょう。
寝るときだけ着る特別な服があると、脳も「寝る時間だ」と認識しやすくなります。
🛒 おすすめアイテム
【オーガニックコットンのベビーパジャマ】肌に優しく、吸湿性の高い素材が睡眠中の快適さをサポートします。[商品リンク]
生後7〜12ヶ月|分離不安との付き合い方
この時期の大きな特徴は「分離不安」の出現。「ママが見えないと不安」という気持ちが強まり、寝かしつけが難しくなることがあります。
1. 安心感を与える工夫
- 添い寝や同室就寝で安心感を与える
- トッポンチーノのようなママの匂いがついた小さな布団を活用
- お気に入りのぬいぐるみを「見守り役」として導入
🛒 おすすめアイテム
【トッポンチーノ】ママの匂いがついた小さな布団で、抱っこからベッドへの移行がスムーズに。いわゆる「背中スイッチ」対策にも効果的です。[商品リンク]
2. 夜間授乳から断乳への移行
生後6ヶ月以降は栄養面では夜間授乳は必ずしも必要ではなくなります。
断乳を考える場合は、徐々に回数を減らしていく「グラデュアル・アプローチ」がおすすめです。

次女は3か月の頃から夜通し寝ていたのですが、長女は1歳ごろまで夜2回起きていました。私の仕事復帰もあったので1歳の誕生日に夜間断乳を決めました。
最初の3日間は大変でしたが、旦那と交代で寝かしつけをしたことで乗り切りました。1週間後には夜通し眠るようになって、ようやく夜通し寝られる日を迎えられました!
3. パパの積極的な参加を促す
ママへの依存度が高まるこの時期こそ、パパの出番です。
パパの低い声や大きな手の温もりは赤ちゃんに別の安心感を与えます。
また、ママが毎回寝かしつけを担当していると「ママでないと寝ない」状態になりがちです。

最初は泣いているのに寝かしつけを担当してもらうのに気が引けていました。しかし、仕事復帰後を考え旦那にも担当してもらうことに。
めちゃくちゃ泣いていて、少し心が痛みましたが頑張ってもらいました。
夜泣き撃退大作戦!症状別対処法
夜泣きに悩まされているママさん、一人ではありません!ここでは症状別の対処法をご紹介します。
身体的不快感をチェック
夜泣きの多くは身体的な不快感が原因です
- 空腹:授乳間隔が空きすぎていないか
- おむつ:濡れていないか、きつすぎないか
- 体温:暑すぎ・寒すぎていないか(首筋や背中で確認)
- 病気:発熱や鼻づまりなどの体調不良がないか

そうは言っても、どれにも当てはまらないのに泣くこともあります。まずは不快感が原因じゃないか確認します。でも原因が思い当たらないときは…諦めましょう。
そういう時期なんです。そう思うと少し気が楽じゃないですか?なんかよくわからないけど泣いてる。私はそう思うことで、自分の精神安定を保っていました(笑)
夜泣きパターン別対応法
泣き方によって対応を変えると効果的です
- 軽い泣き声:すぐに抱き上げず、背中をトントン叩いたり「シー」と言って様子を見る
- 「エーエー」という泣き方:空腹のサインの可能性
- 「ギャーギャー」という強い泣き方:痛みや不快感の可能性
- 「うーうー」という唸るような泣き方:眠りかけの場合が多い

長女は、初めての赤ちゃんだったため泣いたらすぐに対応!が癖になっていました。しかし夜中に泣いたとき、すぐに抱き上げず少し様子を見ていたら再び眠りについたんです!すぐに抱き上げたことで覚醒させてしまい、なかなか寝付けなくしてしまっていたようでした。
実際に効果があった意外な方法
先輩ママたちの体験から生まれた意外な夜泣き対策をご紹介:
- 音楽療法:反町隆史さんの「POISON」←長女には効果抜群でした。次女には効果なし…
- 音楽療法:The Pinkfong の「Baby Shark」←こちらも長女のお気に入りでした
- 扇風機の音:お風呂上がりの髪を乾かすドライヤーや扇風機の音←次女はドライヤーが好きでした
赤ちゃんの寝かしつけで注意したい3つのNG
せっかくの努力が水の泡にならないよう、避けたい行動もチェックしておきましょう。
1. 昼寝を極端に減らす
「夜よく寝てほしい」と昼寝を無理に短くしたり、夕寝を避けたりするのはNG。
赤ちゃんは疲れすぎると興奮状態になり、かえって寝つきが悪くなります。日中の睡眠はしっかりとらせましょう。
2. 就寝前のブルーライト
寝る直前までテレビやスマホ、タブレットの画面を見せるのは要注意。
ブルーライトは睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌を抑制し、入眠を妨げます。

テレビにブルーライトのカバーをかけました。ブルーライトカットだけでなく、このおかげで、子供がおもちゃを投げてしまってもテレビが壊れる心配が減りました!
3. 寝室の明るさ
赤ちゃんの様子を見たくてナイトライトをつけたままにしていませんか?眠りかけの赤ちゃんは光に敏感です。
部屋を暗くすることで、自然と眠りにつきやすくなります。
まとめ
寝かしつけは子育ての中でも特に難しいテーマですが、少しずつ自分の子に合った方法を見つけていくことが大切です。
完璧を目指さず、今日よりも明日が少しでも楽になればOK!
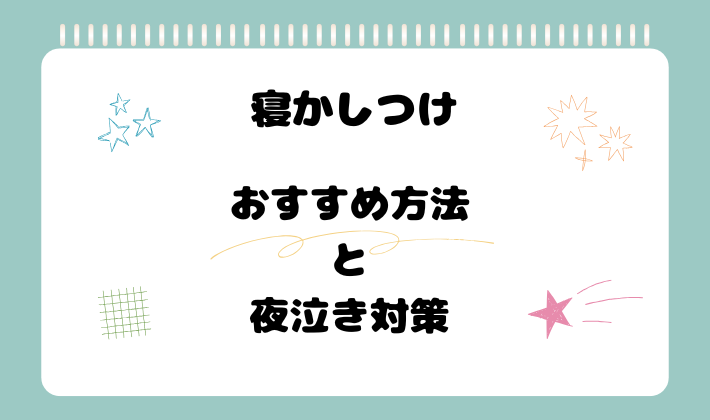
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45140f0e.a3b224bd.45140f0f.801f7861/?me_id=1199397&item_id=10056333&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftansu%2Fcabinet%2Fbono%2F84300053_10.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント