出産準備アイテムリスト
赤ちゃんのお世話スタートセット|初心者ママでも安心の厳選アイテム
赤ちゃんのお世話を始めるにあたり、最初に揃えておきたい基本アイテムをまとめました。
これさえあれば初めてのママでも安心してスタートできる、初心者向けセットです。
ベビー服の基本は短肌着とコンビ肌着です。
短肌着は汗を吸い取る役割があり、3枚以上あると安心です。
コンビ肌着は短肌着の上に重ねて着せる長めの肌着で、季節に応じた温度調節ができます。
どちらも新生児の動きを考慮して、前開きタイプかボタンタイプがおすすめです。

私の場合は、短肌着はほとんど使わずコンビ肌着を使用していました。
迷う方は、まずコンビ肌着のみの購入をおすすめします。
紙おむつとおしりふきは赤ちゃんのお世話に欠かせません。
紙おむつは新生児用を1ケース(約60〜80枚)準備しておきましょう。
おしりふきは厚手でやわらかいタイプを選ぶと、デリケートな赤ちゃんのお肌にやさしいです。
おむつも、おしりふきも出産前から用意しすぎないことがおすすめです。
実際に生まれてみたら予定より大きかった、小さかったという体重の問題やメーカーによって赤ちゃんと相性の悪いものもあります。
出産後、周りに買い物の手助けをお願いできない場合もあるかと思いますが、そうでない場合はまず1パックの購入が無難かとおもいます。
ただし、新生児のおむつはすごいスピードでなくなる(1日8回以上交換した記憶)ため、1週間以内に次の購入が必要かと思います。
沐浴グッズはベビーバスを中心に揃えます。
湯温計、沐浴布、ベビーソープ、湯上りタオルがあれば基本的なお風呂ケアができます。
また、ベビーローションやベビークリームも肌の保湿に役立ちます。
その他、ガーゼハンカチ(よだれふきや授乳時の汚れ防止に)、スタイ(よだれかけ)なども便利です。
最初から全て揃える必要はありませんが、これらの基本アイテムがあると赤ちゃんのお世話がスムーズに始められます。
赤ちゃんとの睡眠環境づくり|安全で快適なベビーベッド選び
赤ちゃんは1日の大半を眠って過ごします。
安全で快適な睡眠環境を整えることは、赤ちゃんの健やかな成長に欠かせません。
まず重要なのはベビーベッドの選択です。
ベビーベッドには床からのホコリやダニから赤ちゃんを守る役割があり、腰への負担を減らして効率的なお世話ができます。
ベビーベッドにはレギュラーサイズ、ミニサイズ、折りたたみタイプなどがあります。
限られたスペースなら省スペースのミニサイズ、実家への帰省が多い家庭なら折りたたみタイプと、ライフスタイルに合わせて選びましょう。
最近はママのベッドとつなげて使えるベッドサイド型も人気です。
ベビーふとんは専用のセットを用意するのがおすすめです。
大人用のふとんは柔らかすぎて赤ちゃんの背骨をサポートできないため、適度な硬さの敷ふとんが必要です。
ベビーふとんセットには掛けふとん、敷きふとん、まくら、カバー類がセットになっています。
ミルクの吐き戻しや、うんち漏れなど思いもかけない洗濯が増えます。
洗い替え用のシーツやカバーも2枚程度あると便利です。
防水キルトパッドは敷きふとんの上に敷いて、汗やよだれ、ミルクのはき戻しから守ります。
季節に応じたタオルケットや毛布も用意しておくと安心です。

私は、ベビーベット卒業後の処分に困るのでは?と思い布団を購入しました。
床においてあるため、上の子やペットがいる場会は心配ですが、落ちたり、挟まる危険性がないのは安心でした。
また、寝返りを始める前の赤ちゃんには、スワドルやおくるみで包むことで安心感を与え、質の良い睡眠をサポートできます。

私はお昼寝をさせる際、寝室で寝かせていたのでベビーモニターを使用していました。
キッチンでモニターを見ながら家事を進められたのは助かりました。
安全で快適な睡眠環境は赤ちゃんの成長を支える大切な要素です。
使いやすさと安全性を重視して、ぴったりのアイテムを選びましょう。
授乳・ミルクタイムを楽にする時短便利グッズ
授乳やミルク作りは1日に何度も繰り返す大切な作業です。
効率的に行うための便利グッズをご紹介します。
母乳育児を予定している方も、万が一の時のために粉ミルクや液体ミルクを少量用意しておくと安心です。
特に液体ミルクは調乳の手間がなく、災害時の備えにもなります。
ほ乳びんは初めは2〜3本あれば十分です。
母乳実感タイプなら母乳との併用もスムーズにできます。
ガラス製は衛生的ですが、プラスチック製は軽くて持ち運びに便利というメリットがあります。
替え乳首も2個以上用意しておくと安心です。

下の子はミルクで育てたので、私は250mLのものを3つ使っていました。
2つでもいいのですが、洗い忘れや夜のミルクの後の洗浄が億劫で…複数個で心の余裕を持っていました。
哺乳瓶の乳首は、成長に合わせて変えていましたよ!
ほ乳びんの洗浄・消毒グッズも必須アイテムです。
専用のブラシや洗剤を使うと効率よく清潔に保てます。
消毒方法は煮沸、薬液消毒などがあります。

私の時には、時短になる電子レンジ消毒器があったのですが、電子レンジは食品以外の加熱を想定していないことから表示が不可となりました。
かわりに顆粒タイプで簡単な薬液消毒のものがでました。
これは非常に重宝しました!
調乳ポットは70℃前後のお湯を保温でき、夜間のミルク作りが格段に楽になる優れものです。
粉ミルクケースと組み合わせれば、深夜でもスピーディーに調乳できます。
外出時にはほ乳びんポーチが活躍します。
保温機能付きのものを選ぶと、お出かけ先でもミルクの温度を保てて便利です。

私は、外出先にはキューブのミルク、水筒にお湯、ペットボトルの水を持って出かけていました。
哺乳瓶ポーチもいいのですが、調乳してから飲むまでに時間が空くのはあまりよくないので、その場で作れるようにしていました。
水筒にお湯を入れて持ち運ぶ場合は、80℃以上で4~5時間保温が可能なものを購入し使っていました。
母乳育児中のママにはさく乳器があると便利です。
手動タイプは安価でコンパクト、電動タイプは効率的に搾乳できます。
さく乳した母乳は専用の保存バッグに入れて冷凍保存も可能です。
母乳育児でも搾乳機は必要ないこともあります。
準備では買わなくても大丈夫です!こんなものもあるんだな~と覚えておくといいです。
授乳の頻度が高い新生児期は、こうした便利グッズを活用して少しでも負担を減らしましょう。
おむつ替えステーション作りと必要な衛生用品リスト
赤ちゃんのおむつ替えは1日に10回以上も行う大切な作業です。
効率的に行えるおむつ替えステーションを作り、必要な衛生用品を揃えておきましょう。
まず、紙おむつは新生児用を1ケース(約60〜80枚)準備しておくと安心です。
おむつ替えの頻度は予想以上に多いものです。
おしりふきは赤ちゃんのデリケートな肌に使うものなので、厚手でやわらかい低刺激タイプを選びましょう。
取り出しやすいようにおしりふきのふたを付けると、片手でもサッと取り出せて便利です。

専用のケースでなくても大丈夫です。ふたは100円均一にもありますが、張り付けるタイプだと粘着が落ちてきました。
少し高いですが、装着するタイプを購入して上の子が赤ちゃんの頃からずっと使用しています(4年くらい?)。
冬場は冷たいおしりふきで赤ちゃんがびっくりしないよう、おしりふきウォーマーも重宝します。
私はおしりウォーマーは購入しませんでした。面倒で…
おむつ替えシートは床や敷物の汚れを防ぎます。
自宅用に洗える布タイプと、外出時用に使い捨てタイプの両方を用意しておくと良いでしょう。

でも、私は洗濯が手間だったのですべて使い捨てを使用していました。
100円均一にもあるし、赤ちゃん用ではありませんが大容量のペットシーツもおすすめです。
使用済みのおむつ処理には専用のゴミ箱が便利です。
臭いが漏れにくい密閉式のものがおすすめです。
外出時には携帯用のおむつ処理袋があると重宝します。
臭いを閉じ込める機能付きの袋なら、周囲に気兼ねなくおむつ替えができます。

パン袋も臭いを閉じ込める機能があるので人気です。
パン袋もいいですが、中身が丸見えなので…自宅ではパン袋、外出先では色付きの袋を使用していました。
また、赤ちゃんの衣類用の洗剤も専用のものを選びましょう。
合成香料や蛍光増白剤を含まない、肌に優しいタイプがおすすめです。
ベビーハンガーも小さな服にぴったりのサイズで、伸びを防ぎます。
これらのアイテムを揃えて、快適なおむつ替え環境を整えましょう。
お出かけデビューに備える|ベビーカー・抱っこ紐の選び方比較
赤ちゃんとの初めてのお出かけは、1ヵ月健診が終わった頃から少しずつ始まります。
そのための移動手段として、ベビーカーと抱っこ紐は必須アイテムです。
それぞれの特徴と選び方のポイントを見ていきましょう。
ベビーカーは移動距離や使用シーンによって選ぶ種類が異なります。A型(フル装備)は新生児から使えるリクライニング機能付きで安定感があり、B型(バギー)は生後7ヵ月頃からの軽量タイプです。
使用頻度が高く長距離移動が多い場合はA型、コンパクトさを重視するならB型がおすすめです。
選ぶ際は実際に折りたたみ操作や押し心地を確認すると良いでしょう。

私は、郊外に住んでいて新生児の頃から使用予定、車が主な移動手段だったためA型を購入しました。
個人的にはベビーカーは急いで購入しなくてもいいと思います。
それよりも、抱っこひもの方が必要順位が高いです。
抱っこ紐は新生児から使える「新生児対応タイプ」と、首がすわってから使う「セカンド抱っこ紐」があります。
新生児期は横抱きができるタイプや、インサート(新生児パッド)付きのものが安心です。
肩や腰への負担分散を考慮した構造のものを選ぶと、長時間の使用も快適です。

私は、新生児から使える抱っこひもを購入しました。
その後、10か月ごろからは体重も重くなり腰も座ったのでヒップシートを別で購入しました。
1歳になってからは、歩き始めじっとしていたくない子だったので簡単に下せるようヒップシートタイプのショルダーを使用しました。
種類もたくさんあるので、自分の生活スタイルに合わせて買うのがいいと思います。
季節に合わせて通気性の良いメッシュ素材や保温性の高い素材を選ぶのもポイントです。
ベビーカーと抱っこ紐に加え、移動中に便利な小物もチェックしておきましょう。
ベビーカー用のレインカバーや日よけ、ドリンクホルダーなどがあると快適さがアップします。
抱っこ紐用のよだれカバーやUVケープも季節に応じて用意すると良いでしょう。
チャイルドシートは法律で6歳未満の子どもに使用が義務付けられています。
退院時から必要なので、出産前に準備しておく必要があります。
車種に合った取り付け方式(ISOFIXかシートベルト固定か)で選びましょう。

私は回転式タイプを購入しました。車が大型ではないので回転できる方が、乗せ降ろしが楽でした。
赤ちゃんのスキンケア&バスタイムグッズ完全版
赤ちゃんの肌は大人の半分以下の薄さで、とてもデリケートです。
適切なスキンケアと心地よいバスタイムで、赤ちゃんの健やかな肌を守りましょう。
生後1ヵ月頃までは「沐浴(もくよく)」と呼ばれる、ベビーバスを使った入浴方法が一般的です。
ベビーバスは赤ちゃんの体を安定させて洗えるよう設計されています。
空気でふくらませるタイプや、シンクで使えるコンパクトタイプなど様々な種類があります。
バスマットを併用すると赤ちゃんが滑りにくく、より安全に沐浴できます。
湯温計を使って38℃前後の適温を保ち、湯上りタオルで素早く包んであげましょう。
沐浴布(もくよくふ)やガーゼは、赤ちゃんの胸元にかけて安心感を与えたり、優しく体を洗うのに使います。
ベビーソープは刺激の少ない専用のものを選びましょう。
固形せっけんよりも泡タイプの方が使いやすいです。
沐浴後は赤ちゃんの肌を保湿するために、ベビーローションやクリームでケアします。

私は湯温計は使用しませんでした。手で確認し熱くなければ大丈夫だろうと感覚で沐浴していました。
沐浴布は少し小さめのタオルや手ぬぐいのようなもの、ガーゼを使っていました。
首すわり前は、お風呂に入れるのがとても怖かったです。ネットで支えられるベビーバスだったのでとても助かりました。
綿棒は耳や鼻、へそのお手入れに必須です。赤ちゃん用の細いタイプを選びましょう。
爪切りは赤ちゃん専用の安全なデザインのものがおすすめです。電動タイプは初めての方でも安心して使えます。

私は、はさみタイプを使用していましたが慣れるまでは少し怖かったです。爪は1週間に2~3回切った気がします。
びっくりするほど新陳代謝がよく、すぐに伸びるのであらかじめ用意しておくのをおすすめします。
体温計は脇下や耳で測れるデジタルタイプが便利です。
赤ちゃんのお部屋の温湿度管理も重要です。
温湿度計を置いて、室温は夏場25〜28℃、冬場は20〜23℃、湿度は50〜60%を目安に調整しましょう。
鼻づまりがある時には鼻吸い器を使って、赤ちゃんが快適に呼吸できるようサポートします。

赤ちゃんの鼻水吸い器もいろんな種類があり、購入に迷いましたが管理が楽なものを選びました。
使用感ももちろんですが、使用後の洗浄の楽さを重視しました。
これらのアイテムを揃えて、赤ちゃんが気持ちよく過ごせる環境を整えましょう。
コスパ重視!予算別おすすめ出産準備セット
出産準備は決して安くはないものですが、賢く選べば予算内でも必要なものをしっかり揃えられます。
予算別におすすめのセットをご紹介します。
まず5万円程度の予算なら、最低限必要なアイテムを厳選して揃えましょう。
必須品はマタニティインナー(ブラ2枚、ショーツ2枚)、入院グッズ(パジャマ、産褥ショーツ)、赤ちゃんの肌着セット、おむつ、沐浴グッズの基本セットです。
ベビーカーやベビーベッドはリサイクルショップやレンタルも検討すると予算内に収まります。
10万円程度の予算なら、上記に加えて抱っこ紐や授乳クッション、ベビーモニターなどの便利グッズも追加できます。
質の良いチャイルドシートやベビーカーといった安全に関わる大型アイテムに予算を集中させるのもおすすめの方法です。
15万円以上の予算があれば、より快適な育児環境を整えられます。
電動鼻吸い器や調乳ポット、さく乳器などの時短アイテムを揃えると、育児の負担が大きく軽減されます。
また高機能なベビーカーやチャイルドシートなど、長く使うものに投資するのも良いでしょう。
どの予算であっても、まずは必須アイテムから揃え、あとから買い足せるものは様子を見てから購入するのが賢い選択です。
また、ベビー用品専門店のポイントシステムやセールをうまく活用すれば、より効率的に準備できます。
予算と必要性のバランスを考えながら、無理のない準備を進めましょう。
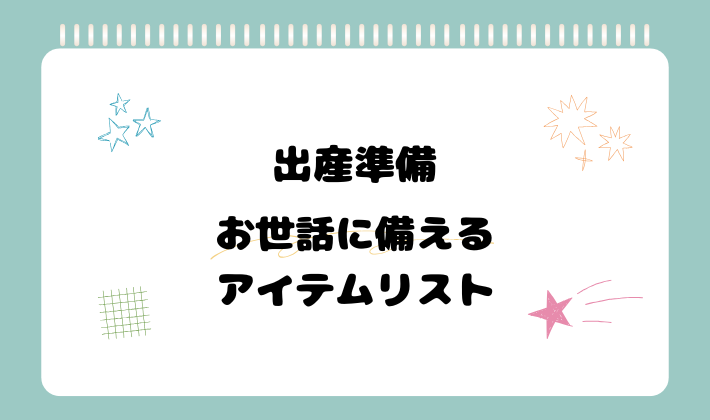
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4509c2e6.d832ff0f.4509c2e7.0edafcc5/?me_id=1345403&item_id=10002232&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fponopono%2Fcabinet%2F22-13%2F2205090_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45c54243.6d0c3410.45c54244.ff54f2cd/?me_id=1412350&item_id=10002835&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcomodocasa%2Fcabinet%2Fevery_makers%2Fyamatoya%2Fimgrc0082248348.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/465687f2.e7cbae8d.465687f4.8e9389c3/?me_id=1300680&item_id=10000025&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsecupcs%2Fcabinet%2Fimage%2Fpb%2Ftb53k_pb2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4510c941.fd724a8b.4510c942.c2365a0c/?me_id=1212232&item_id=10037087&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnetbaby%2Fcabinet%2F019%2F4902508121019.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4656900d.7d0a5db3.4656900e.6ded7e0b/?me_id=1412305&item_id=10001060&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fatlas-online%2Fcabinet%2Fatpbs%2Fatpbs_spec00_500.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/465697bb.2a42c116.465697bc.69829003/?me_id=1216285&item_id=10053416&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpockybear%2Fcabinet%2F056%2F9651501.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46569b1b.36bf0cb1.46569b1c.74cc8f89/?me_id=1370933&item_id=10000747&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsuperpack%2Fcabinet%2Fimgrc0089954516.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46569cb9.98467c9f.46569cba.f94df52c/?me_id=1338192&item_id=10000098&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbos-shop%2Fcabinet%2F07611451%2Fbaby_ss200_2set.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4510de1c.32eb0f07.4510de1d.c927ea27/?me_id=1406218&item_id=10000007&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fbabybjorn%2Fbb-gallery%2Fbabycarrier-mini_thumb_202411_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4656a578.4b108e46.4656a579.d3a58a27/?me_id=1403544&item_id=10000009&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frealize-store2020%2Fcabinet%2F09961721%2F11270334%2F11367924%2Fimgrc0092844234.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4570cf0a.38b2b1d9.4570cf0b.30279fbf/?me_id=1355731&item_id=10000171&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fslotre%2Fcabinet%2Fentry5point%2F10000123_entry5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4511e5b9.4dc42ca3.4511e5ba.21d45f1f/?me_id=1374439&item_id=10002137&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpigeon-shop%2Fcabinet%2Fthumb%2Fthumb2%2F1032018.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント