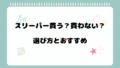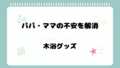出産を控えたパパママにとって、赤ちゃんの寝床をどうするかは大きな悩みとなります。
ベビーベットを購入するか、それともベビー布団にするか、迷われている方も多いのではないでしょうか?
この記事では、それぞれのメリットを詳しく解説し、あなたの家庭環境に合った選択をお手伝いします。
赤ちゃんの睡眠環境を考える
新生児期から必要な睡眠アイテムの選び方
赤ちゃんは一日の大半を睡眠で過ごします。
そのため、安全で快適な睡眠環境を整えることは、健やかな成長につながります。
ベビーベットとベビー布団はどちらも魅力的な選択肢ですが、家庭の状況や赤ちゃんの特性に合わせて選ぶことが大切です。
睡眠アイテムを選ぶ際には、安全性・使いやすさ・お手入れのしやすさなどを総合的に考慮しましょう。
ベビーベットとベビー布団の基本的な違いとは
ベビーベットは床から高い位置に赤ちゃんを寝かせるため、お世話がしやすく安全性も高いのが特徴です。
また、柵があるため転落防止になりますが、ある程度のスペースが必要です。
一方、ベビー布団は床や畳に直接敷いて使うもので、スペースを取らず、片付けも簡単です。
場所を選ばず敷けますが、床からの高さがないので埃やハウスダストの影響を受けやすいという違いがあります。

高さがあるベビーベットならハウスダストの影響は少ないけど、高さがある分転落には気を付けないといけない…悩みますよね~
家庭環境別!最適な選択ポイント
赤ちゃんのアレルギー対策に適しているのはベビーベット
アレルギーに配慮する必要がある家庭では、ベビーベットがアレルギー対策として効果的です。
アレルギーの原因となるハウスダストやダニは床上約30cm以内の空間に多く漂っています。
ベビー布団では直接この空間で赤ちゃんが眠ることになるため、アレルゲンを吸い込む量が増えてしまいます。
特にハイタイプのベビーベットなら、床板の高さが70cmほどあり、床近くのアレルゲンから赤ちゃんを守ることができます。
アレルギーの心配がある家庭では、この点を重視して選ぶとよいでしょう。
限られた部屋のスペースを有効活用するならベビー布団がおすすめ
マンションやアパートなど限られたスペースで生活する家庭では、ベビー布団の方がスペースを有効活用できます。
ベビーベットは常に一定のスペースを占めますが、ベビー布団は使わないときには収納することができるため、部屋を広く使えます。
ただし、スペースを気にするならもう一つの選択肢として、収納棚付きのベビーベットもあります。
ベッド下の空間を収納として活用できるタイプなら、おむつやベビー用品などをすっきり片付けられるので、全体としてスペースの節約になることもあります。
寒い季節の冷え対策に強いのはベビーベット
冬場の寒さ対策を考えるなら、ベビーベットの方が赤ちゃんを床冷えから守れます。
床には冷気がたまりやすく、どんなに暖房をつけても足元は冷たいままということがよくあります。
ベビー布団では床の冷たさを直接感じてしまいますが、ベビーベットなら床から離れた位置で眠るため、床冷えの影響を受けにくくなります。
また、暖かい空気は上に昇るという性質から、ベビーベットの高さがある分、より暖かい空間で赤ちゃんを眠らせることができます。
特に寒冷地にお住まいの方や、冬の寒さが厳しい地域にお住まいの方は、この点を考慮するとよいでしょう。

私は普段はベットで寝ていました。出産後は、赤ちゃんのお世話のために和室に私の布団とベビー布団をを並べてお世話していましたよ。
家族との添い寝や川の字で眠りたい場合はベビー布団が最適
パパママと一緒に川の字で寝たいと考えているなら、ベビー布団の方が家族の添い寝に適しています。
赤ちゃんとのスキンシップは親子の絆を深める大切な時間です。
ベビー布団なら、パパとママの間に赤ちゃんを寝かせる「川の字」スタイルが取りやすく、常に赤ちゃんの様子を確認できる安心感もあります。
ただし、添い寝の際は寝返りで赤ちゃんを圧迫しないよう注意が必要です。
寝相が悪い方や深酒の習慣がある方は、安全面を考慮してベビーベットの使用も検討しましょう。
上の子がいる家庭で安全を確保するならベビーベットが便利
兄弟姉妹がいる家庭では、上の子からの安全を確保するためにベビーベットが適しています。
小さなお兄ちゃんやお姉ちゃんは好奇心旺盛で、つい赤ちゃんに触れたり、上に乗ったりしてしまうことがあります。
悪気はなくても、不意な事故につながる可能性があるため、柵のあるベビーベットで赤ちゃんを守るのが安心です。
同様の理由で、室内ペットを飼っているご家庭でも、ベビーベットを使うことで安全を確保できます。
一人目の時は布団で大丈夫だったとしても、二人目以降はベビーベットを選ぶ家庭が多いのはこのためです。

我が家は下の子が生まれたときに上の子が3歳である程度、言葉が理解できる年齢だったため、ベビー布団を使用しました。兄弟姉妹の年齢差によってはベットの方が安心かもしれませんね。
添い寝もできる便利なベビーベットの選び方
添い寝をしたいけれど安全面も確保したいという方には、「3面オープン」タイプのベビーベットが理想的です。
このタイプは両側と足元の柵が開くので、大人のベッドに接して置いて使うことができます。
ママのベッドとベビーベットの高さを合わせれば、ママは自分のベッドに、赤ちゃんはベビーベットに寝ながら添い寝が可能です。
このスタイルなら、布団での添い寝で心配される圧迫の危険もなく、安全に添い寝を楽しめます。
また、両側の柵が開くタイプなら、パパとママのベッドの間に置いて使うこともできるため、家族の寝室環境に合わせて柔軟に対応できます。
和室の雰囲気を損なわないベビーベットの活用法
和室で生活されている方にとって、洋風のベビーベットは違和感があるかもしれません。
しかし、和室でも使いやすい「サークル兼用タイプ」のベビーベットもあります。
このタイプは床板の高さを26cmほどまで下げられるため、和室でも違和感なく使えます。
床に座った状態や座布団に座った状態からでも赤ちゃんのお世話ができるほか、座椅子やクッションに座りながら赤ちゃんの様子を見ることもできます。
和室の雰囲気を大切にしながらも、ベビーベットのメリットを活かした育児をしたい方におすすめです。

なんとなく、ベビーベットは高さがあって大きい。そんな知識しかありませんでした。2人目の時にもう一度調べたら、1人目を生んだ時にはなかったような画期的なグッズなどがどんどん増えていてびっくりしました。
おすすめ商品ガイド
人気のベビーベット
最近のベビーベットは機能性とデザイン性を兼ね備えたものが増えています。
特におすすめなのが、ハイタイプの「ツーオープン」タイプのベビーベットです。
床板の高さが70cmほどあるため、立ったままの姿勢で赤ちゃんのお世話ができ、腰への負担が軽減されます。
また、横だけでなく足元も開閉できるツーオープンタイプなら、おむつ替えの際にも便利です。
収納棚付きのタイプを選べば、ベッド下のスペースを有効活用でき、かさばるベビー用品もすっきり収納できます。
ベビーベットは2歳ごろには使用できなくなります。購入していますとサイズが大きく処分に困る可能性もあります。
あまり値段は安くないですが、レンタルを検討してもいいかもしれません。
快適な眠りをサポートするベビー布団
ベビー布団を選ぶなら、適度な厚みとクッション性を持ち、洗濯できるものがおすすめです。
最近では抗菌防臭加工が施されたタイプや、カバーが取り外せて洗濯できるタイプなど、お手入れのしやすさにも配慮された商品が人気です。
冬は保温性の高いもの、夏は通気性の良いものなど、季節に合わせて使い分けられる布団セットも便利です。
また、床冷え対策として、断熱性の高いマットを敷くと赤ちゃんの快適な睡眠環境づくりに役立ちます。
あなたの家庭に最適な選択は?
まとめ:赤ちゃんの睡眠環境に合わせたベビーベットとベビー布団の選択ポイント
ベビーベットとベビー布団、どちらを選ぶかは家庭環境や優先したいポイントによって変わってきます。
アレルギー対策や腰痛予防を重視するならベビーベット、スペースの有効活用や添い寝を重視するならベビー布団と、それぞれに適した状況があります。
どちらを選ぶにしても、赤ちゃんの安全と快適さを最優先に考えることが大切です。
できれば出産前に準備を整え、赤ちゃんを迎える準備をしっかりとしておきましょう。
よくある質問Q&A:ベビーベットとベビー布団に関する疑問解決
Q: ベビーベットはいつから必要ですか? A: 理想的には出産前に準備しておくと安心です。新生児期から使えるタイプも多く、早めに環境を整えておくことをおすすめします。
Q: ベビーベットはいつまで使えますか? A: 一般的には1歳半から2歳頃まで使用できます。成長に合わせて床板の高さを調節できるタイプなら、より長く使えることもあります。
Q: ベビー布団の下に敷くマットは必要ですか? A: 特にフローリングの場合は、床からの冷えや硬さを緩和するためにマットを敷くことをおすすめします。断熱性と適度なクッション性があるものを選びましょう。
Q: ベビーベットとベビー布団、両方用意した方がいいですか? A: 予算と空間に余裕があれば、状況に応じて使い分けられるよう両方用意するのも良い選択です。ただし、必ずしも両方必要というわけではありません。
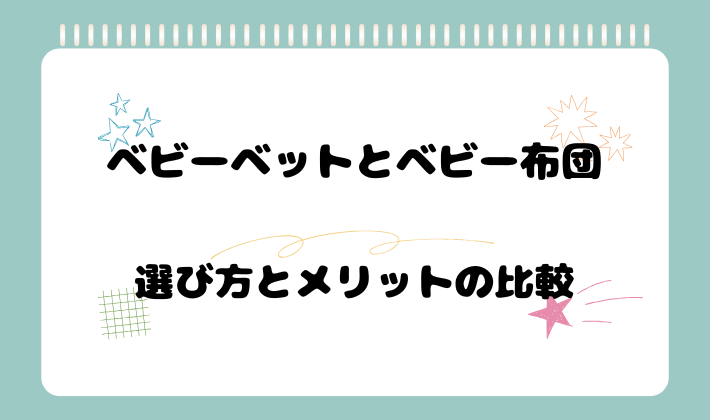
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45c54243.6d0c3410.45c54244.ff54f2cd/?me_id=1412350&item_id=10002835&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcomodocasa%2Fcabinet%2Fevery_makers%2Fyamatoya%2Fimgrc0082248348.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4510c941.fd724a8b.4510c942.c2365a0c/?me_id=1212232&item_id=10011463&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnetbaby%2Fcabinet%2F700%2F401700.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4791d59c.75dbb164.4791d59d.7088bce3/?me_id=1214435&item_id=10021827&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnicebaby%2Fcabinet%2Fbed%2F100-0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44ecf511.4b23ab62.44ecf512.a4ebabc5/?me_id=1237131&item_id=10000625&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhashkude%2Fcabinet%2Fnbd%2Fogwa%2Fn1103-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)